-
最近の投稿
アーカイブ
カテゴリー
投稿日カレンダー
2025年12月 日 月 火 水 木 金 土 « 11月 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
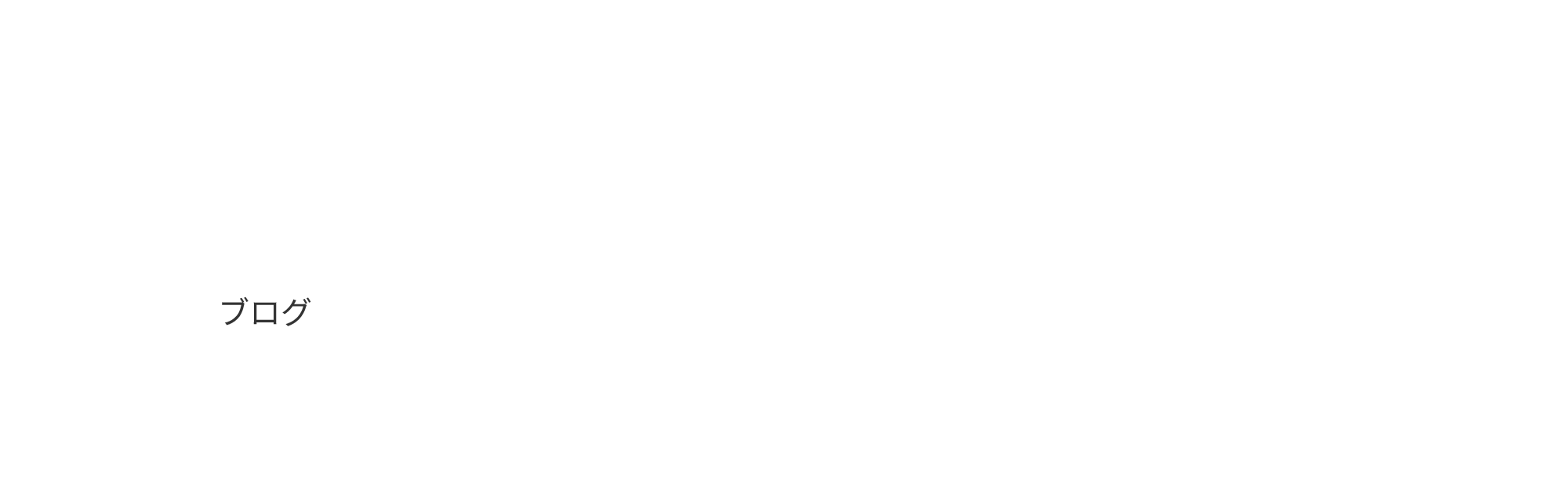
皆さんこんにちは!
株式会社ハリケーンマスター、更新担当の中西です。
~看板デザインの進化と街づくり~
看板は今、ただの広告ではなく“文化”へと変わりつつあります。
テクノロジー・環境・デザイン感性――すべてが交差する中で、
これからの看板製作はどこへ向かうのか。
液晶・LEDディスプレイを使ったデジタル看板(サイネージ)が急増中。
動きのある映像で情報を伝え、時間帯や季節に応じて内容を変えることが可能です。
・飲食店:昼はランチ、夜はディナー告知
・不動産:最新物件情報をリアルタイム表示
・自治体:災害情報・観光案内
“生きている看板”が、街の情報インフラになりつつあります。
環境意識の高まりから、再生樹脂や木材を使った看板も増えています。
また、太陽光発電と連動した自立型LEDサインも登場。
“光らせる”だけでなく、“地球に優しく見せる”時代です。
塗料もVOCフリーや耐候型水性塗料を採用し、
屋外でも人にも自然にもやさしい設計が主流になっています。
企業や店舗の価値観を「言葉なしで伝える」時代。
ロゴ・フォント・質感・レイアウト――
その一つひとつに“ブランド哲学”が宿ります。
たとえば、
・クラフトビール店の手描き風サイン=手づくり感
・IT企業のミニマルサイン=未来感・機能性
・老舗旅館の銅板サイン=歴史と信頼
看板は、「この場所がどんな想いで存在しているか」を語るストーリーテラーです。
看板の集合体が街並みを形づくる。
だからこそ、調和と個性のバランスが大切。
派手すぎず、でも埋もれない。
視界に心地よく入るデザインが、
街全体の“印象”を変えていきます。
看板職人は、単に広告を作る人ではなく、
“街の風景をデザインする人”なのです。
看板製作は、アートでありテクノロジーであり、人の想いをつなぐ仕事。
1枚のサインが、街を照らし、人を導き、企業を語り、文化を残す。
これからも、看板づくりは変化し続けるでしょう。
けれどその根底にはいつも、
「誰かの目に届き、心に残るデザインを」という職人たちの想いが息づいています。
![]()
皆さんこんにちは!
株式会社ハリケーンマスター、更新担当の中西です。
~LED看板と光のデザイン🌃~
夜の街で、ひときわ目を引く光。
それは“光る看板=サイン”の存在です。
LEDやネオンが進化し、今では光そのものがデザインの一部になっています。
今回は、照明看板の魅力と技術を紹介します。
たとえば同じ白でも、色温度が違えば印象が変わります。
2700K(暖色):カフェ・レストランなどに柔らかさ
4000K(中白色):企業・事務所に清潔感
6500K(昼光色):薬局・病院に明るさと安心感
「光の色は、言葉以上にメッセージを伝える」。
光が生み出す雰囲気が、お店のブランディングを左右します。
LEDモジュールには、防水性・輝度・消費電力など多様なタイプがあります。
屋外看板には「防水IP65以上」が必須。
また、輝度が強すぎると眩しく感じるため、設置環境に合わせて調光も必要です。
近年では“RGBフルカラーLED”を用いたアニメーション看板も登場。
時間帯やイベントに合わせて光を変える“動くデザイン”が注目されています。
アクリル内照式看板では、光ムラが最大の敵。
職人はLEDの間隔を正確に配置し、反射板や拡散板で光を均一化します。
点光を面光に変えるノウハウは、経験によって磨かれます。
「光を均一に見せる」ための裏側には、
緻密な計算と繊細な感覚が息づいています。
LEDは寿命が長いとはいえ、経年で暗くなることもあります。
また、電源ユニット(トランス)の劣化も要注意。
定期的に点灯確認・配線チェックを行い、
早めの交換でトラブルを防ぐ。
“光の持続”もデザインの一部なのです。
光る看板は、ただの照明ではなく街のアクセント。
人の目を引き、心を動かす“光の演出”こそが、サインデザインの醍醐味です。
夜の街に輝くその一瞬の美しさに、
無数の職人とデザイナーの手が宿っています。
![]()
皆さんこんにちは!
株式会社ハリケーンマスター、更新担当の中西です。
~“手と技”️~
完成した看板を見るとき、そこには「光」と「デザイン」があります。
でも、そこに至るまでには、現場の職人たちの技術と努力が詰まっています。
今日は、看板製作の“裏側”を、現場の目線でお伝えします。
看板の製作図はミリ単位で作られます。
しかし、現場では壁の凹凸・下地の材質・配線位置など、図面通りにいかないことが多い。
そこで必要なのが「現場合わせ」。
職人はその場で寸法を測り、取付金具を加工し、
“美しく・安全に・確実に”設置できるように即対応します。
まさに、理論と経験の融合。
この判断力が、看板職人の真価です。
工場では、毎日さまざまな音が響きます。
レーザー切断の光、金属曲げのプレス音、アクリル研磨の匂い…。
ステンレス文字の面を0.1mm単位で磨き、
アクリル板を熱で曲げ、LEDを規則正しく組み込む。
“看板製作”とは、機械と手仕事のハイブリッド。
自動加工機で精度を出し、人の手で質感と美しさを整える。
この手順こそ、人の温度を持ったモノづくりです。
現場取付の日。
作業車には看板本体、工具、ボルト、配線、照明機材…。
数百キロの看板を高所に吊り上げることもあります。
安全帯・ヘルメット・ハーネスを装着し、
風速や天候を確認して作業開始。
ボルト締めひとつにも「設計強度」があり、
トルクレンチで規定値を確認。
一人が気を抜けば、すぐに事故につながります。
チームワークと声かけ、段取りの正確さが全て。
“静かな緊張感”の中に、職人の誇りが光ります。
LED看板の取付では、光ムラや明るさのバランスも大切。
モジュールの間隔を均一に配置し、
ケーブルを目立たせずに隠す工夫を行います。
電気工事士資格を持つ職人が配線を確認し、
防水コネクタでショートを防止。
通電試験で光の強さを調整し、初めて“完成”します。
作業を終えて通りを離れるとき、
ふと振り返ると、自分たちの作った看板が光っている。
その瞬間、「今日も良い仕事をした」と感じます。
看板は人の記憶に残る“形のない仕事”。
でも、それを見上げる誰かが笑顔になる。
それが、職人にとって最高の報酬なのです。
![]()
皆さんこんにちは!
株式会社ハリケーンマスター、更新担当の中西です。
~看板製作という仕事の本質~
街を歩いていて、まず目に入るもの。
それは建物そのものよりも“看板”かもしれません。
カフェの木製サイン、夜の交差点で光るネオン、企業ロゴが誇らしげに掲げられた社屋サイン。
看板は「建物の顔」であり、「第一印象」を決める重要な要素です。
今回は、そんな“看板製作”の世界を、企画・デザイン・施工の三方向から深く掘り下げます。
目次
看板の役割は、単に「店の名前を出す」ことではありません。
人が何気なく見て、「どんな雰囲気のお店なのか」「信頼できそうか」「入りやすいか」
そうした感情を数秒で伝えるのが看板の力です。
つまり、看板とは“24時間働く営業マン”。
しかも、言葉を使わずに印象を届ける“非言語コミュニケーション”の道具なんです。
看板製作の第一歩は、ヒアリングです。
お客様の業種、立地、ターゲット層、競合環境などを丁寧に把握します。
たとえば――
・住宅街の美容室なら「柔らかさ」や「親しみ」
・オフィス街の弁護士事務所なら「信頼感」や「品格」
・工場や倉庫なら「機能性」や「視認性」
伝えたい印象によって、フォント・素材・配色・照明まで全て変わります。
デザインは“美しさ”ではなく、“伝達の設計”なのです。
看板の命は素材選びにあります。
主な素材には以下のようなものがあります
| 素材 | 特徴 | 用途 |
|---|---|---|
| アルミ複合板 | 軽量で加工しやすい | 壁面・袖看板 |
| ステンレス | 高級感・耐久性抜群 | 企業サイン・外壁ロゴ |
| アクリル | 光透過性があり演出力◎ | 内照式看板・入口サイン |
| 木材 | 温もりと個性 | カフェ・美容室・宿泊施設 |
| LEDモジュール | 長寿命・省エネ | 夜間照明・電飾看板 |
同じロゴでも、素材と表面仕上げで印象はまったく変わります。
“触感で伝えるデザイン”が、プロの仕事です。
看板が完成するまでには、数多くの工程があります。
1️⃣ 打合せ・現地調査
2️⃣ デザイン提案・修正
3️⃣ 版下データ作成(Illustratorなど)
4️⃣ カッティング・出力・加工
5️⃣ 立体成形・塗装・電装組み込み
6️⃣ 現場取付・照明調整
この中で最も大事なのは、デザインと現場の整合性。
設計図面通りに取り付けられなければ意味がありません。
だからこそ、製作スタッフと施工チームの連携が命です。
屋外看板は、風・雨・紫外線・地震などあらゆる自然環境に晒されます。
そのため、構造設計や強度計算も重要。
ボルト固定、アンカー深さ、重量バランス、電気配線保護…。
一つでも欠ければ事故につながります。
「見た目が良い」だけでは終わらない、“安全設計の美学”がそこにあります。
街並みを形づくるのは建物だけではありません。
看板のデザイン統一や明るさのバランスは、その地域の雰囲気を左右します。
例えば京都の町家では「控えめな木製サイン」
東京・渋谷では「光と動きの演出」
それぞれに“街のルール”と“文化”があります。
看板は、単なる広告ではなく“街との対話”。
その土地らしさを大切にすることが、良い看板づくりの第一歩です。
看板製作は、デザイン・工学・心理・美学のすべてが詰まった総合芸術です。
そこには「伝える力」と「守る力」、そして「街への想い」が込められています。
たった一枚の看板が、人の足を止め、心を動かす。
それがこの仕事の何よりの魅力です。
![]()
皆さんこんにちは!
株式会社ハリケーンマスター、更新担当の中西です。
~時代とともに進化!~
昭和の商店街を思い出すと、手書き文字の木製看板や、味のあるペンキ文字が思い浮かびますよね。
当時は職人が一文字ずつ筆で描いており、その温かみが魅力でした。
しかし現代では、デジタル技術の進化により看板制作も大きく変化しています✨。
UVプリント、レーザーカット、LED発光、そして**デジタルサイネージ(電子看板)**など、
表現の幅は無限大に。
「デジタル」と「アナログ」が共存しながら、新しい時代の“魅せ方”が生まれています。
今、街中で注目を集めているのがデジタルサイネージ。
動画やアニメーションを使って動きのある広告を表示でき、
季節や時間帯に合わせて内容を変えることも可能です⏰。
たとえば、カフェなら朝は「モーニングセット☕️」、
夜は「ディナー&ワイン」を表示するなど、
リアルタイムにメッセージを更新できる点が大きな魅力なんです!
さらにSNSと連携すれば、「#本日のおすすめ」などの投稿も表示でき、
お客様とのつながりを強化できます。
最近では“サステナブル”の観点から、
リサイクル素材やソーラー発電LEDを使ったエコ看板も増えています。
電気をほとんど使わない蓄光サインや、植栽と一体化した緑化看板など、
「環境にやさしく、街にも美しい」新しいかたちが次々と登場しています✨。
こうした看板は、企業の“イメージアップ”にも大きく貢献。
「環境を考えている会社」としてのブランディング効果も抜群です。
今の時代、看板は“情報を伝える”だけでなく、“SNSでシェアされる”ことも意識されています✨。
思わず写真を撮りたくなるような立体文字やネオンサイン、
夜に光るフォトスポット的デザインなど、
「映える」要素が集客力を大きく左右します。
つまり、看板はもはや“インスタの背景”でもあり、
お客様が投稿した写真が最高の広告になる時代なんです。
看板制作業は、技術とセンスが進化し続けるクリエイティブな世界。
アナログの温もりと、デジタルの表現力が融合することで、
「見る人の心を動かす看板」が次々と生まれています。
あなたの街のあの看板も、きっと職人とデザイナーが想いを込めた“作品”です✨。
次に通りかかるとき、少し立ち止まって見てみてください。
そこには時代とともに進化する看板の物語が刻まれています。
![]()
皆さんこんにちは!
株式会社ハリケーンマスター、更新担当の中西です。
~街をデザインする仕事!~
街を歩いていて、思わず目を引くおしゃれな看板に出会ったことはありませんか?
看板は、お店の第一印象を決める“顔”のような存在です。
どんなに素敵な商品を扱っていても、看板が魅力的でなければ通り過ぎてしまう人も多い…。
それほど、看板のデザインは集客に直結する重要なポイントなんです。
看板制作業とは、その「第一印象」を形にするプロの仕事。
デザイン力だけでなく、設置場所・視認性・耐久性など、アート×テクノロジー×マーケティングの要素が融合しています。
一口に“看板”といっても、種類はさまざま
壁面看板:建物の外壁に設置。遠くからでも見やすくインパクト大!
スタンド看板:店舗の入口に置くタイプ。季節やキャンペーンごとに変更しやすい
ネオン・LED看板:夜でも光って目立つ✨近年は省エネLEDが主流!
車両ラッピング:移動広告として人気
懸垂幕・横断幕:イベントや新装開店など短期的なPRにも◎
それぞれに目的があり、「誰に」「どんな印象を与えたいか」でデザインが変わります。
たとえば、飲食店なら“食欲をそそる色合い”を、サロンなら“清潔感と上品さ”を意識するなど、
看板はまさに“お店の世界観を伝えるツール”なんです。
実は看板づくりには心理的効果も大きく関わっています。
赤やオレンジは「元気」「活発さ」を連想させ、
青は「信頼」「安心感」、
緑は「癒し」「自然」を感じさせる色としてよく使われます。
さらに、フォントの形や文字の大きさ、余白の取り方も重要。
人の目線の動きや、歩行スピードを考慮して配置を決めるなど、
細かな設計力が成功の鍵となります。
看板制作は、ただ作るだけの仕事ではありません。
その場所を通る人、見る人の“感情”に寄り添うことが大切です。
「ここ、気になるな」「入ってみようかな」
そんな小さなきっかけを生み出すことができる。
つまり、看板は街のコミュニケーションツールでもあるのです✨。
看板制作業は、デザイン力+技術力+人の心をつかむ力が求められる、まさに“総合芸術”。
街を歩くたびに「あの看板かっこいいな!」と思える瞬間があったら、
その裏には看板職人の熱い想いと緻密な計算があることを、ぜひ思い出してみてください。
あなたの見ているその看板――
誰かが「伝えたい」を形にした作品かもしれません。
![]()
皆さんこんにちは!
株式会社ハリケーンマスター、更新担当の中西です。
~やりがい~
看板は、店舗や企業の「顔」として、集客やブランドイメージに直結する存在です。
シンプルな表札から大型ロードサイン、最新のデジタルサイネージまで、多種多様な看板が街を彩っています。
看板製作業は、こうした「人とビジネスをつなぐ第一印象」をつくる仕事であり、単なる物づくりを超えて 情報発信とデザインの融合 を担っています。
近年、看板製作業に求められるニーズは多様化しています。
店舗競争の激化
飲食店や小売業で、通行人の目を引くデザイン性・視認性の高い看板が必須に。
ブランドイメージの強化
ロゴやカラー、フォントを活かしたデザインで、企業の世界観を表現する役割。
デジタル化の進展
LED・デジタルサイネージが普及し、映像や動きで情報を届けるニーズが拡大。
地域密着の情報発信 ️
商店街や観光地での案内看板やイベントPRなど、地域を活性化するための製作需要。
安全・規制対応 ⚖️
屋外広告物法や自治体条例に基づいた設置、安全性への配慮も強く求められている。
看板製作に携わる人々が感じるやりがいには、次のようなものがあります。
街を彩る誇り ️
自分が製作した看板が街中に設置され、多くの人の目に触れる達成感。
お客様の成功に貢献できる
新店舗のオープンやリニューアルで「看板のおかげでお客様が増えた」と喜ばれる瞬間。
デザインと技術の融合
デザイン力と製作・施工技術の両方を活かし、形のないアイデアを具体化できる楽しさ。
多様な案件に挑戦できる
小さなカッティングシートから巨大な屋上広告、最新デジタルサイネージまで幅広く対応できるのが魅力。
社会貢献性の実感
道路標識や公共施設の案内板など、人々の暮らしを支える役割を担えること。
例えば、新規オープンする飲食店のオーナーから「目立つ看板をつけたい」と依頼を受け、完成後に「おかげで来店数が増えました!」と報告をもらうとき。
また、観光地で案内看板を設置し、地域活性化に貢献できたとき。
「人の流れを生み出し、街や企業の価値を高める」 その瞬間に、やりがいと社会的ニーズが重なります。
今後、看板製作業にはさらなる発展が期待されています。
データ活用:通行量や時間帯に応じて表示を変えるスマートサイネージ
エコ素材の導入:環境に配慮したリサイクル材・省エネLEDの採用
デザイン性と安全性の両立:美しさと法規制対応を兼ね備えた看板
地域連携:観光PRやまちづくりの一環としての看板製作
看板製作業は、
人とビジネスをつなぐ顔を作る仕事
デザインと技術を融合させるものづくり
社会や地域を支える誇りある仕事
という大きなやりがいがあります。
同時に、
店舗競争・ブランド力強化
デジタル化・地域活性化
安全性・環境配慮
といった強いニーズがあり、これからも街の景観と経済活動を支える存在であり続けるでしょう✨
![]()
皆さんこんにちは!
株式会社ハリケーンマスター、更新担当の中西です。
~変遷~
目次
看板の歴史は古く、江戸時代の商店前に掲げられた「木製の屋号板」や「絵看板」にまで遡ります。
当時の看板は、職人が手描きで一文字一文字、または絵を描き上げたもの。
視覚的にわかりやすく表現することで、識字率が低い人々にも伝わる工夫がされていました。
看板製作は「書や絵の技術」を持つ職人の仕事であり、まさに手仕事による芸術でもありました。
戦後復興と経済成長に伴い、街には数多くの店舗や企業が並ぶようになります。
それに合わせて看板製作も大きく進化しました。
シルクスクリーン印刷の普及による大量製作
ネオンサインの登場で、夜間でも目立つ広告が可能に
プラスチックやアクリル素材を使った軽量化・量産化
この時代は「目立つ」「量をこなす」ことが重視され、看板製作業は商業発展を支える重要な産業となりました。
バブル経済と消費文化の拡大に伴い、看板はただの広告ではなく「ブランドイメージ」を体現するものへ。
カラフルなグラフィックデザイン
立体的なチャンネル文字(箱文字)の普及
内照式看板による視認性アップ
この時代、看板製作業には デザイン力と企画力 が求められるようになり、ただ作るだけでなく「どう魅せるか」を提案する仕事へと発展していきました。
パソコンや大型プリンターの普及により、看板製作は大きく変革します。
インクジェットプリントによるフルカラー出力
カッティングシートを用いた施工の簡便化
LEDの普及で省エネかつ長寿命の光る看板が登場
これにより、従来では難しかった精細なデザインや短納期対応が可能に。
看板製作はよりスピーディで柔軟な産業へと進化しました。
近年では「動く看板=デジタルサイネージ」が主流の一つに。
映像・アニメーションで訴求力を高める
ネットワーク経由で複数拠点のコンテンツを一括更新
タッチパネル機能によるインタラクティブ広告
従来の静的な看板から、情報をリアルタイムで発信できるメディアへと役割が拡大しました。
一方で、昔ながらの木製看板や手描き文字も「レトロブーム」や「クラフト感」を求めるニーズとして復活し、多様性が広がっています。
未来の看板製作は、さらに次のような方向に進化していくと考えられます。
IoT連携型看板:人の流れや天候に合わせて表示内容を変える
AR/VR広告:スマホをかざすと看板が立体映像になる
エコ素材の活用:リサイクル資材や太陽光発電型看板
地域密着デザイン:地域文化や観光と一体化した看板づくり
看板製作業は、
手描き看板の職人技術から始まり
印刷・ネオンによる大量生産
デザイン性・ブランド性の強化
デジタル化とLEDの進化
デジタルサイネージやIoT連携
と大きく変遷してきました。
今や看板は「ただの目印」ではなく、街を彩り、ブランドを表現し、人と社会をつなぐメディアです。
これからも看板製作業は、時代のニーズに応じて進化し続けることでしょう✨
![]()
皆さんこんにちは!
株式会社ハリケーンマスター、更新担当の中西です。
~長くキレイに効く看板~
作って終わりでは、看板は価値を発揮しません。清掃・点検・劣化診断・更新計画、そしてデジタルサイネージの運用設計まで回してこそ“売上装置”。実務で使える年間計画とチェックをまとめました。
目次
毎月:外観チェック(汚れ・シート浮き・ヒビ)/点灯時間のログ
四半期:清掃(中性洗剤+柔らかいクロス)/ビス緩み/シーリングひび
半年:電装点検(電圧・電流)/PSU温度/虫侵入の有無/照度測定
年1:塗膜チョーキング確認/看板周辺の植栽・障害物見直し/法面・占用更新
3–5年:シート再施工 or クリア再塗装/LEDの**減光(L70)**を見てモジュール更新判断
面材:アクリル・ポリカはアルコール/溶剤NG、中性洗剤で優しく
フィルム:高圧洗浄を近距離で当てない/エッジから水を入れない
金物:粉体塗装の小傷はタッチアップ、腐食は素地出し→防錆→再塗装
シーリング:痩せ/割れは打替え。雨仕舞いを最優先
温度:盤内・PSUの温度ロガーで夏季ピークを把握
電流不均衡:LED回路のバラつきは早期の色ムラ要因→配線/PSUゾーニングを見直し
振動:袖看板・屋上看板はワイヤの鳴き/金物の緩みを重点点検
表示面:UVでの退色が目に付いたら部分張替えより全面貼替が仕上がり◎
LED:ランニングは安いがPSU寿命がボトルネック。PSU先行更新が停電リスクを下げる
塗装:チョーキング粉が手に付いたら再塗装サイン
ハード
輝度2500–4000nit(設置環境で)/アンチグレア/IP定格/防塵フィルタ
熱対策:ファン/ヒートパイプ/直射日光向けの日よけ
停電復旧:自動再起動・電源投入順制御
ソフト&コンテンツ
コンテンツカレンダー(季節・イベント・時間帯別)
A/Bテスト:静止画→動的、CTAの文言、QR位置を検証
明るさ自動調光(照度センサー)で夜間グレア抑制
万一:ネット断でも再生するローカルプレイリストを設定
測定
表示回数・タッチ/QR流入・近接センサーの滞在時間→店舗のCVと突合
点灯スケジュール最適化:深夜は30–50%減光
LED効率の見直し(古いモジュール→高効率品へ)
太陽光+タイマーでサイン電源一部賄い
リサイクル:アルミ母材の回収、アクリル端材の分別
眩光:向き・角度・遮光板・ルーバーで近隣対策
雨音・ビビリ:中空板・金物の共振にはスポンジ/ブチルでダンピング
景観:色温度と彩度は周辺と調和。行政ガイドラインを事前確認
盤内温度/PSUファン/フィルタ清掃
面板割れ/反り/黄変
取付金物(錆/緩み/二次固定ワイヤ)
シーリング・雨仕舞い・ドレイン
点灯ムラ/ちらつき/色ズレ
塗装のチョーキング/剥離
周辺障害物(樹木・新設看板)
点灯スケジュール/減光設定の最適化
デジタルのログ(稼働率・再起動回数・温度アラート)
ケース:夜眩しく苦情→来店減
対策:照度センサー導入+減光カーブ再設定/配光を壁面反射型へ変更
結果:苦情ゼロ、歩留まり率+12%、電力-28%
ケース:色褪せ・ロゴ違い
対策:色基準書(DIC/PANTONE+発光実機)を作成、承認フローを一本化
結果:再施工ゼロ、製作リード-20%
![]()
皆さんこんにちは!
株式会社ハリケーンマスター、更新担当の中西です。
~見つかる・読める・来たくなる~
良い看板はデザインの出来だけでなく、設置場所・視認条件・構造・施工・運用の総合格闘技。この記事は、現場でそのまま使える実務の順番とチェックリストをまとめた“実装ガイド”です。
目次
見る人の条件を数値化します。
視認距離:歩行者10–30m/車両30–120m(道路制限速度と見合わせ)
視認時間:歩行者2–5秒、車両1–3秒が目安
視線の高さ:歩行者1.4–1.6m、ドライバー1.1–1.3m
接近角度:正対/斜め進入/コーナーの死角
周辺輝度:昼(直射/日陰)・夜(街灯/対向光)
障害物:樹木・電柱・バナー・駐車車両
設置条件:壁強度・下地材・アンカー可否・引込み電源・避難通路・占用区分
調査は写真+簡易スケッチで残し、想定歩行/走行ルート動画も撮ると設計が一気に楽に📸
主語1つ・目的1つ・行動1つ(例:〈自家焙煎コーヒー〉〈本日OPEN〉〈この先右折〉)
誘導情報:矢印・距離・階数・駐車場P表記は迷わせない表現で
ブランド要素:ロゴ・コーポレートカラー・トーン&マナーを最小要素で反映
経験則
読める文字高さ=視認距離(m)÷30 ≒ cm
例:60m先なら約2cm、120m先なら約4cmが目安
走行環境では**×1.3〜1.5倍**を推奨
ストローク(線の太さ)は文字高さの10–15%
配色
高コントラスト(白/黒、黄/黒、白/濃紺)を基本に
背景が明るい街路では濃色地+明色文字、逆に夜間は明色地+暗色文字でハロー抑制
グラデ・写真背景は文字まわりに1.5〜2文字分の余白🧭
盤面:アルミ複合板(軽量・寸法安定)/ステンレス(高耐食)/鋼板(溶融亜鉛+焼付塗装)
表示:塩ビシート(屋外5–7年)/キャストシート(耐候◎)/アクリル切文字/カルプ立体
照明:LEDモジュール/テープ(4000–6500K)、拡散板はアクリル乳半 or ポリカ拡散
塗装:粉体焼付 or 2液ウレタン/屋外は耐候クリアで退色を遅らせる
電装:防水等級IP65以上、結線は防水コネクタ+ドリップループで浸水防止
下地確認:RC/ALC/木造でアンカー種別を変更(ケミカル・オールアンカー等)
異種金属接触腐食:SUS×アルミの間に絶縁ワッシャ
風荷重:突出看板・袖看板は支柱径・ブラケット長・ベースプレートを計算
落下防止:二次固定(ワイヤ補助)/ボルトはゆるみ止め+トルク管理
配光:内照はムラ<20%を目標/外照はウォールワッシャーで均一化
制御:タイマー+明るさセンサーで自動点灯/消灯、深夜は減光(30–50%)
保守:電源(PSU)は外付けスペースに集約し交換性を確保
屋外広告物:地域ごとの条例で区域・サイズ・高さ・色彩など制限あり
必要書類:縮尺図・構造図・位置図・写真・工作物確認・承諾書 等
近隣調整:占用・はみ出し・眩光クレーム予防に事前説明が効果的
企画・現調・見積
基本図(レイアウト・サイズ・文字高)
構造図・電気図・申請
データ入稿(カラーマッチング)
部材手配・工場製作(QC:寸法・発光ムラ・端面処理)
施工(安全KY→墨出し→取付→通電)
完了検査(水平・垂直・照度・写真)→引渡し📑
作業届・交通誘導・立入規制・高所/感電対策
取付芯・水平器・レーザーで通り確認
アンカー締付トルク・増し締めペイント
電圧・電流・漏電・絶縁
表示面の気泡/シワ/継ぎ目
周辺清掃・養生撤去・近隣あいさつ 🙇♂️
視認率(通行人への簡易聞取 or カメラ解析)
入店誘導率(設置前後のCV)
夜間照度(看板面中央/周辺)
問い合わせ増分(QR/専用電話で計測)
保守工数/年(清掃・点検・修理)
情報過多で読めない → 主語1行・行動1つに削減
昼は良いが夜は眩しい → 減光制御&拡散板変更
色が合わない → 指定色はDIC/PANTONE+実機発光サンプルで承認
たわみ・ぐらつき → ブラケット補強、支点位置見直し
![]()